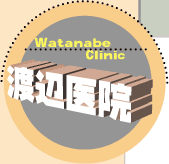渡辺医院より毎月一回発行されている『健康新聞』から、記事の一部を紹介します。(2001.1.25更新)
『健康新聞』第371号より
西医学による
インフルエンザの予防と根本的治療法
【原因】
インフルエンザの原因については、現代医学ではウイルスだとしているが、本当のところは明らかになっていない。『ワクチンが効果がない』のもそのためである。
西医学では、夏の間に発汗し、水分、塩分、並びにビタミンCを失ったのに、これを適切に補給していないと足の故障を起こしている。そこで風邪をひくことになる。その他、過労や心労、食べ過ぎ、飲み過ぎ等があげられる。
このような原因で、全身の血液循環が不良となり、静脈血やリンパ液のうっ血、うっ滞を来たし、処々に停滞していること。皮膚の働きが弱く体温調節が円滑にいかないこと。鼻や咽喉の粘膜が弱くて細菌等に侵され易いこと、肝臓や腎臓の解毒器官が十分に働かず。腸に宿便が停滞すること。これらのために体液が酸性に傾きやすいこと等がその原因となる。
したがって「予防法」は、平素、発汗の適正な処置を行うこと。すなわち水分と食塩並びにビタミンCを十分にとること。大気浴療法と温冷浴を行い皮膚の働きを丈夫にして、六大法則を実行すれば風邪をひくこともなく、インフルエンザにかかることもない。
【治療法】
(1)芥子泥湿布
100gの芥子に対し、同容量のお湯(摂氏55度)を入れてやや固めにドロドロに溶いて布に塗る。上にガーゼか和紙を置き、これを胸部に貼る。時間は20分以内。発赤してヒリヒリすればよろしい。
これは咳をおさめ、痰を溶かして排出し、胸痛を止め、肺炎を予防する。子供の場合は芥子とうどん粉を半々に混ぜて用いる。
最も効果を現わす温度は摂氏55度であって、50度になれば効力を減じ、100度以上、又は30度以下では効果がない。
(2)脚湯法
高熱、微熱、あらゆる熱患者に有効であり、インフルエンザのウイルスが香港A型でもB型でも、ソ連A型でもどれでも構わない。全てに有効である。
下肢(膝から下)を温めて発汗させる発汗療法である。発汗したら生水、食塩、ビタミンCを補給すること。
一度実行すると熱が却って上がる場合もあるが、次第に下がるので心配する必要はない。
脚湯法は大きなバケツに摂氏40度のお湯を入れ、これにふくらはぎから下をつけること5分間、体は毛布や布団で包み寒くないようにして、5分毎に一度宛差湯で湯温を上げ、41度で5分間、42度で5分間、43度で5分間、計20分間暖めるのである。そして20分経ったら脚を引き上げて軽く拭ったあと、脚を1〜2分間冷水に漬ける。
摂氏14度ならば2分間
摂氏16度ならば2分半
摂氏18度ならば3分間
水から揚げたならば、脚と水気をよく拭き取って休む。
脚湯法は、発汗させるのが目的である。終って発汗したら、水分、塩分、並びにビタミンCの補給を必ず行うこと。インフルエンザの予防には、大気浴療法と温冷浴を実行し、夏期の発汗の対策として、十分に水分、塩分、並びにビタミンCを補給すること。これは柿茶、生野菜食がよろしい。
治療法としては、咳や痰には芥子湿布、熱のある場合には脚湯法を行うこと。これが最善である。私は多くのインフルエンザの患者さんを全てこの方法で治した。生体一者であり、症状即療法である。ウイルスの種類は問わない。頑固な気道感染症(咽喉炎、気管支炎、気管支肺炎、肺炎)には抗菌剤か抗生物質を用いることは当然のことである。

|