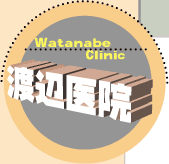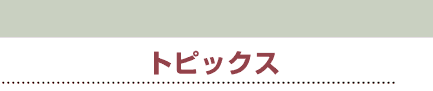肩を左右いずれかに傾けたまま歩いたり、前かがみのまま長時間パソコンに向かっている人を良く見かける。このような姿勢は背骨のずれにつながりやすい。背骨のずれは単に肩こりや腰痛だけでなく、内蔵疾患との因果関係も指摘されているだけに、放置は禁物だ。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「背骨のずれ、ゆがみは、万病のもとと言って差し支えない」と言い切るのは渡辺医院(東京・中野)の渡辺正医院長。自然治癒力を高める西式医学を長年研究している渡辺氏は、「背骨がずれている人は体調に異変をきたしやすく、胃腸や肝臓に疾患を抱えていることも多い」と解説する。
背骨のずれとは、背骨を構成する骨のいずれかが本来の位置からねじれたり傾いたりする「亜脱臼」という状態を指す。
どうして背骨がずれるのか――。人間は直立歩行で重い頭を支えなければならず、歩くたびに頭に衝撃がかかる。これを緩和するために、横から見た背骨はS字状の曲線を描いている。その代わり、軟骨でつながった骨の一つ一つは、ずれやすい構造にもなっている。特に現代人は長時間、背中を丸めてパソコンに向かったり、姿勢の悪いままテレビを見たりするので、余計にずれやすい。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
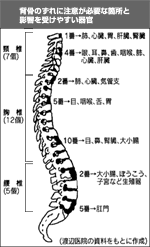 |
画像をクリックすると
拡大図が表示されます |
背骨は合計32〜34個の骨からなる。上から順に7個の頚椎(けいつい)、12個の胸椎(きょうつい)、5個の腰椎(ようつい)および5個の仙骨、3〜5個の尾てい骨だ。
これらの骨のずれた場所と影響を受けやすい器官との間には、別表のように相関関係があるとされる、例えば、頚椎の一番上にある「頚椎一番」がずれると、肺、心臓、胃、肝臓、腎(じん)臓に疾患があらわれやすい。胸椎の十番目なら目、鼻、腎臓、大小腸、ぼうこう、生殖器などだ。
骨のずれと器官のこうした因果関係について、整骨、整体の関係者の多くは、それぞれの骨から伸びた神経が、背骨のずれによって圧迫を受けて働きが鈍り、関係の深い器官の活動に支障が出るためとみている。
背骨がずれるメカニズムについて、鍼灸(しんきゅう)・整体を手掛ける庚和治療院(東京・小平市)の寺井徹院長は、筋肉のこりが影響することに着目する。長時間同じ姿勢を続けると筋肉が硬直し、近くの背骨が筋肉の硬直した方向にずれややすくなる。整骨・整体の施術前には、筋肉を十分ほぐさなければ骨は再びくずれていく」と指摘する。
意外なことに、スポーツでも背骨はずれやすくなる。水泳など左右の動きのバランスがとれた競技であれば問題ないが、ゴルフ、テニス、野球のように体の片側に偏った動きを繰り返す競技は注意が必要だ。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
背骨がずれているかどうかは整形外科などでレントゲンで撮ればわかるが、日常生活ではなかなか自覚できない。そこで現代人は、自ら生活習慣に気を付けてずれを予防し、ちょっとした運動で矯正を心がけることが望ましい。
まず、日ごろの姿勢をチェックしてみる。無意識に左右のどちらかに偏っていることがないだろうか。電車を待っているときに体重をかける足が決まっていたり、足を組む方向がいつも同じだったり、といった具合だ。いつも同じ側の手でかばんを持つ人もそうだ。こうした偏りをなくし、正しい姿勢をとることが予防の基本になる。
寝る前に簡単な運動を行い、一日のずれをとってから就寝するのも効果的だ。渡辺院長は
「金魚運動」を薦める。両手を頭の後ろで組み、腰を左右に振る運動だ。二人一組で足を他人に振ってもらうのもよい。また、寺井院長は両ひざをおなかを抱えて丸めたり、足をつけたまま両ひざを90度に立て、体の左右に倒す運動が効果的という。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
(追補)渡辺医院長
背骨のズレを治すには、前記の金魚運動がもっとも効果があるが、本当のところ、
六大法則をすべてを実行することが一番望ましい。即ち、平床、硬枕、金魚運動、毛管運動、合掌合蹠、背腹運動である。その中でも、特に平床、金魚運動と合掌合蹠を行うこと。卓効がある。
最近多発している腰痛科座骨神経痛、月経不順等の婦人病科疾患、更には難産、不妊症等々の疾患もすべて六代法則、特に平床、金魚運動、合掌合蹠法を実行することによりすべて解決する。
合掌合蹠法はもっとも手軽で確実な無痛安産法でもある。
※六大法則についての詳しい説明はこちら