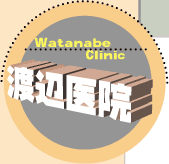渡辺医院より毎月一回発行されている『健康新聞』から、記事の一部を紹介します。(2002.12.31更新)
『健康新聞』第423号より
「病気を予防するのも治すのも自分の力」(2)
- 薬はその自然治癒力を弱めるもの
- 四大原則・六大法則の西医学健康法
- 毎日の実行が生命力を充実させる
医学博士渡辺 正氏に聞く
「健康ナビ」副編集長
嶋屋佐知子
(株)セルフケアニュース
◎かぜをひいたら
もし風邪をひいたら西医学ではどうするか。体内から水分、塩分、ビタミンCを失ったのを適切に補給していないと、足の故障を起こし、体内に老廃物がたまる。
この老廃物を排せつして解消するために、発熱、発汗が起き、カゼをひくわけです。その他、全身の血液循環が不良で、血液がところどころに停滞していること。厚着していて皮膚が弱く、体温調節がうまくいかないこと。肝臓の解毒器官が十分に働かず、腸に宿便がたまっていること。などのため全身が不調になるのが、カゼの原因です。カゼをひいて頭が痛いときは、まず便通をつけて腸をキレイにし、なるべく冷やさないようにして、暖かく、安静にしていること。午前は足首の交互浴を行い、午後三時以後に脚湯法を行う。脚湯法で汗をかいたら、水分、塩分、柿茶、生野菜汁、レモンなどでビタミンCを補う。発汗後は寝巻きを着替えてからだを冷やさないように。解熱剤で熱を下げたり、薬をくり返すと体は弱くなるのです。
薬ではなく、治すのはあくまでも本人の自然治癒力であることを忘れずに。四大原則・六大法則の西式健康法。毎日の実行が生命力を充実させます。
西医学は、現行医学のように、対症療法で病気を根本的に治そうとするものではありません。人間を全体として、つまり生体一者として診る医学です。だから薬に頼らないで病気を治したり、病気を寄せつけないからだづくりを提案することができるのです。
西医学の基本
西医学をご説明すると、生命力は、皮膚、栄養、四肢、精神の4つの柱で支えられており、これらを充実させることが大切です。衣服でおおわれ、本来の機能が果たせなくなった皮膚を活性化させる。カロリー本位でなくバランスのよい食事法で栄養に配慮する。
四肢を働かせて血の循環を良くする。そしてこれらを統合する精神の力を付ける。前向きな思考をし、口に出し、潜在意識に働きかけます。
西医学はこれらを四大原則といいます。そしてそれぞれを充実させるために、西式の食事法があり、四肢には毛管運動、皮膚には裸療法、温冷浴などの方法などが編み出されました。また重要な健康体操として六大法則と呼び、朝晩2回実行して、文化生活によって弱まった自然治癒力をのばし、健康なからだづくりをしていくのです。六大法則とは平台寝台、硬枕使用、金魚運動、毛管運動、合掌合蹠、背後運動の6つ。西医学を実行する基礎になるものです。病気の時も六大法則は活用できます。生涯続けたい健康づくりの方法です。
◎足首交互浴法(足首以下の温冷浴)
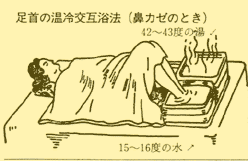 【方法】
【方法】
図のように、洗面器または適当な器二個に湯(摂氏四十度〜四十二度)と冷水(十四〜十六度)とを用意して、両足のくるぶしまでをつける。
湯→水→湯→水→湯→水というように、一分間ずつ交互に各三回の温冷浴をする。必ず湯より始めて、終わりは水とする。なお湯より水に入れ、水より湯に入れる際は、雫を軽く拭うことを忘れてはならない。水虫や凍傷の場合は三十分くらい行う。
◎脚湯
【効能】
高熱 微熱 凡ゆる熱患者に応用すべきもので、時刻としては午後三時以後が宜しい。一度実行すると、熱が続いて出ることがあっても心配する必要はない。
発汗したら生水、食塩並びにビタミンCを補給すること。
腎臓病 水腫 糖尿病等にも有効で、咳のあるのも脚湯で止まる。
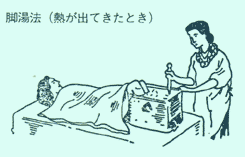 【方法】
【方法】
脚湯器又は深いバケツを用意して、お湯を入れ、仰臥して、ふくらはぎから下をつけ、膝から上は毛布や掛ぶとんで覆う。温度を上げるには、電熱で温めるか、やかんを用いて熱湯をたえず注入すること。
「温度と時間」は五分間毎に温度を一度ずつ上げ、四十三度で止める。
- 摂氏四十度にて五分間
- 摂氏四十一度迄上げて五分間
- 四十二度まで上げて五分間
- 四十三度まで上げて五分間
通算二十分前後、脚を湯から出してよく拭い、用意の水を一回だけ浸ける。この時の冷水の温度と時間は次の要領で行う。
- 摂氏十四度ならば二分間(一回)
- 摂氏十六度ならば二分半(一回)
- 摂氏十八度ならば三分半(一回)
水から揚げたならば、足の水気をよく拭いとって安臥する。
脚湯法は、映画「ゾラの生涯」の中でゾラが風邪を治すのに、脚湯をやるところが三回出ています。
我が国に於いても文久二年(西暦1862年)(第十四代徳川家茂の時代)刊行の今村了庵著「医事啓源」にこの事がある。

|