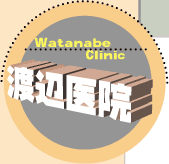◎「脳梗塞」の2つの種類
脳梗塞は一本の血管やその枝が完全につまった場合をいいますが、この中には「脳血栓」と「脳塞栓」とがあります。
血栓は脳の血管がその場で血液が固まって、閉塞する場合で、塞栓は心臓またはそれより脳に近い血管(頸動脈など)についていた血液のかたまりが離れたり、そのほかの物質が血流にのって脳動脈の中に入ってつまらせる場合です。起きるときの症状は似ている点もあります。
≪症状≫ 脳血栓は比較的高齢者で動脈硬化や高血圧がある人に、なんらかの前触れ的症状(一時的な手足のまひ、しびれ、めまい、物忘れ、イライラなど)があって終わりに大きな発作となることが多い。
「脳塞栓」は急激にはじまり、前触れなく、一瞬のうちに訪れ、塞栓の場合は、心臓病、特に脈の乱れの強い心臓弁膜症(多くはリウマチ性)のある人に多く起こり、必ずしも高齢者とは限りません。
また、脳血栓は、夜中に起こって朝気づくことも珍しくありません。「脳梗塞」は、「脳出血」とくらべると一般に意識障害が軽い傾向もありますが、病巣の大きさや場所によっていろいろです。
一つの比較的大型の脳梗塞の場合、それが完成されたかたちとしては、意識障害の片まひ、片側の感覚障害、言語障害(吃音障害や失語症)、排尿障害などがみられ、脳出血の場合と類似しています。
一方、ごく小さい脳梗塞があちこちに多数起こっている場合には、パーキンソン病の時に見られるような症状の手のふるえ、筋肉の硬くなること、動作が遅くなることなどがあらわれたり、痴呆が目立ってきたりすること(多発性脳梗塞型痴呆とか脳動脈硬化性痴呆と呼ばれる)もあります。
このような小梗塞が多発することは、脳塞栓の場合はほとんどみられず、むしろ高齢者の脳梗塞か、脳動脈硬化による脳溢血の場合にみられたものです。
脳梗塞の診断には、脳出血の場合と同様にX線CTが有力です。ただし、脳出血の診断とちがって、脳梗塞としての画像は二〜三日から一週間ほどたってからあらわれてくるので、発作直後の確定は困難ですが、出血でないという証明にはなります。
脳出血の場合には、X線CT撮影で直ちに診断が確定できます。