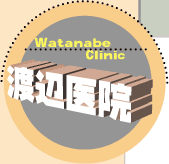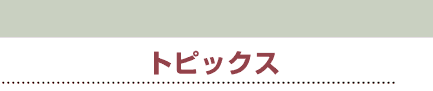|
|
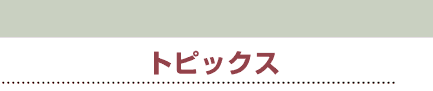
|
渡辺医院より毎月一回発行されている『健康新聞』から、記事の一部を紹介します。(2003.8.28更新)
『健康新聞』第448号より
西医学健康法
保健養生六十三則(1)
医学博士 渡辺 正
- 不良姿勢をとらぬこと。起立、活動中の姿勢に注意し、就寝時の敷布団は、なるべく薄く、硬いものにし、厚くやわらかきを避け、脊椎骨の変歪を正し、脊椎の不正圧迫を予防すること。
- 換気不十分にして、新鮮なる空気、日光を妨げるような住宅、および土地を避けること。
- 住宅は、湿潤なる土地、北面の土地、塵埃、毒ガスの発生する土地、化学工場、火葬場などの風下の土地などを避けること。
塵埃捨場、沼沢、溝側など不潔物の堆積せる土地の埋立地、天然ガスの発生などは、有毒ガスを発生し、健康上有害であって、知らず知らずの間に、その影響を受けることを知ること。
- 厚着の習慣をさけること。夜具の掛布団は、なるべく薄く軽きものを用いること。
- 冬期、外出するときは、戸外にて外套を着、帰宅するときは戸外にて外套を脱ぐこと。
- 夏季といえども、二五分以上裸体にならないこと。
- 足袋、手袋、襟巻などを常用しないこと。
- 暖炉、ストーブ、炬燵、湯タンポなどの常用をしないこと。
- 懐炉、腹巻、都腰巻などをしないこと。
- 冬期の暖房は、なるべく摂氏一五、六度(華氏六〇ないし六一度)以上にしないこと。
- 密閉せる地下室などのごとき高温室内、または、冷凍室のごとき低温室には、四〇分以上いないこと。
- 扇風機、氷柱の常用をさけること。
- タワシ、荒縄、ブラシまたは硬き手拭、タオルのようなものにて、皮膚を摩擦しないこと。このような行為は、皮膚に炎症を起こし、やがては肺臓ガンなどの原因をなすから、やめなければならない。
- 有毒ガスを吸入、またはそれに接触した時は、ただちに裸療法または温冷浴によって、これを解消すること。
- 汗知らず、亜鉛華、シッカロールなどを常用しないこと。赤ちゃんのお尻のタダレは、柿の葉の煮汁をうすめて用いれば、ただちに治り、これをときどき用いれば、タダれることはない。
- 発汗に際しては、生水、食塩並びにビタミンCの補給を忘れないこと。食塩に対しては、一ヵ月一、二回の塩抜き日を励行し、食塩過剰をさけること
- 発汗による水分の欠乏は、血液中にグアニジンを堆積するから、二十時間以内に生の清水の飲用によって、これを解消しなければならない。
人間の血液中のグアニジン含有量は、正常値において、血液一〇〇グラムに対し、〇.一ないし〇.二ミリグラム(私は、いつでも〇.〇八ミリグラム)であり、これが十倍になると尿毒症を起こして死ぬから、注意しなければならない。これには生の清水さえ飲めば解消する。
- 発汗における食塩の喪失(汗一〇〇グラム中の食塩は〇.三〜〇.七、平均〇.五グラム)は、必ず足に故障を起こすから、これを二十時間以内に、補給しておき、同時に毛管運動により足をなおすことをわすれてはならない。食塩が過剰となっても、足と腎臓とを障害するから、一ヶ月に一、二回の塩ぬきを励行すること。
- ビタミンC欠乏(汗一〇〇グラム中、七〜十二ミリグラム、平均一〇ミリグラムを含む)は、歯を痛め歯槽膿漏を起こし、壊血病の原因をなすから、生野菜、果物、とくに蜜柑、もしくは柿茶で、これを補給せねばならない。
- 白砂糖の過剰に注意し、その極量を守ること。黒砂糖ならば白砂糖の三倍まではよろしい。病人、ことに肺結核患者は、むしろ砂糖を厳禁するほうがよろしい。
- 氷水、アイスクリームのごとき冷たいものを大量に飲用せざること。多用すると肝臓を障害する。
- 熱きにすぐる飲用物を常用せざること。総入歯の人はとくに注意を要す。これを常用することは、食道および胃粘膜を傷害し、ガン発生の要因をなす。
香川県高見島村は、摂氏九八度(華氏二〇九)の粥を食う習慣があり、ガンの発生率は全国第一であり、ついで奈良県、和歌山県が朝粥を食するため、ガンが多い。これは、朝粥が悪いのではなく、その温度が高すぎるから、食道や胃の粘膜を痛めるためである。
- 美食、飽食すると、肝硬変、肝肥大をきたし、腎臓を過労し、肥胖症、高血圧、動脈硬化症、心臓障害、糖尿病などを起こす。もろもろの疾病の原因となるのは、美食、飽食によることが多い。
- 朝食廃止、昼夕の二食主義とすること。朝食を摂ると、老衰を早め、咽喉に炎症を起こす。
- 午前十時半以前には、固形食を摂らぬこと。流動食は、ある程度さしつかえないが、やはり有害であるから、摂らないほうがよい。
- 朝食廃止にこしたことはないが、できれば、軽い食餌を少量にすること。微温の粥、トーストなどで我慢すること。いっそ思い切って、やめたほうがよろしい。
- 下痢する場合、水分(生の清水)を十分に補給すること。下痢止め、その他これに類似の薬剤は用いないこと。大きな下痢の場合は、なるべく続く二食を絶食すること。
- 吐瀉ともに起こる場合は、充分に吐き、充分に下し、全身を温めて水(生の清水)分を飲めるだけ飲むこと。
- 不合理な食餌を摂らないこと。季節はずれのもの、珍しいものに注意すること。
- 午後九時すぎて、硬いもの、不消化のものを過食しないこと。
- 通常の夕食が遅れるほど、その量を減じ、とくに午後十二時前後は、食事を中止するか、微温の粥色とすること。夜業者の午後十二時の食餌も、消化しやすいものを少量とすること。
- 疲労時に、通常食事を連続せざること。極度に疲労した時は、むしろ食餌を摂らないほうがよい。
- 便通三日以上ないときは、通常食餌をしないこと。このようなときは、食餌を半減するか、断食するがよい。
- 便通のないときは、腹部味噌湿布を施すこと。
- 食欲のないときは、絶対に飲食してはならない。かつ葡萄糖の注射も害がある。
(つづく)

|
|
|
|