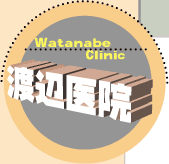◎理想的な食事
通常の食事は、主食10対副食10の割合。副食は野菜3、肉類3、海草類3、果物1が理想です。野菜は必ず生野菜を摂ること。ただし、酸とアルカリの関係からマンションの高い部屋や高台に住んでいる人は酸性度の高い肉類を、また低地にすむ人はアルカリ度の強い野菜を多めに摂るようにして下さい。
理想的な食事を毎日毎日きちんと摂ることはなかなか大変です。外食の機会の多い都会では実行できることの方があるいは、少ないかもしれません。そこで、次に述べる方法で三週間に一度くらいの割合で食事の総決算をして下さい。
- 断食日 一日生水と柿茶だけで過ごすが、普通は代用として寒天断食法でもよい。
- 野菜かゆ食日 調味料を使わない米と野菜だけのかゆだけを食べる日です。
- 生食日 食塩を全く摂りません。生食日とかゆ食日を兼ねてもよい。
- 無糖日 砂糖を全く摂りません。かゆ食日を兼ねてもよい。
- カレー日 ライスカレーを食べる日。十日に一度くらい昼食に摂る。のどと食道に芥子(からし)療法をしているのと同じことです。
- 五目飯日 月に一度くらい、種々の色素を補給します。
- 小豆飯 月に二回くらい、、ビタミンB類の補給となります。
・やせが太る
病弱だったりしてやせており太りたい人は、米粒大のバター、チーズを次のようにして、夕食後1、2時間してから摂るとよい。
1回目は1粒だけ3日間、その次は2粒を3日間、3回目は3粒を3日間という具合に3日おきに1粒ずつ増やしていき、10粒までいきます。これで、約1ヵ月たつわけですが、これをまた1粒から始めて計3回つまり3ヵ月間続けます。望む体重に達したところで止めるとよい。
・ビタミン、ミネラルをたっぷりと
黒豆粉(いって粉にひく)、そば粉、小麦粉、とうもろこし粉を各1合をいりながら混ぜ、これに白、黒、赤のごま(いって粉にひく)各3勺とこんぶ粉5勺を加え、冷めてから黒砂糖を少し加えます。これは七福香ばしと呼ばれ、ビタミン、ミネラルの補給のほか、甲状腺ホルモンの異常にも良い。毎日、茶サジ2杯服用します。
・白砂糖はこれが限度
体重1kg当たり、生後半年までは0.1g、1年までは0.2g、その後10歳までは0.3g、それから20歳までは0.4g、20歳以上は0.5g、これが1日に摂る白砂糖の上限です。
この数字は体重1kgについての許容量ですから、体重をかけて目安にして下さい。
例えば、体重20kgの8歳の子供だったら3g、70kgの30歳なら35gになります。角砂糖1個の大きさが6gです。ただし黒砂糖は白砂糖の3倍まではOKです。ミネラルが豊富ですし、腸からの吸収を遅らせる成分も入っているからです。
・食中毒はこうして予防する
食中毒を起こしやすい食べ物には、次のようなものがあります。
- <ふぐ> 肝臓、卵巣、血液にフグ毒が多い。四月以降は要注意。
- <カキ> 七、八月の産卵期は中毒しやすい。A型肝炎ウィルスに汚染されているケースもあるから。そうした指摘がある場合は要注意。火を通せば問題はありません。
- <天ぷら> 脂質分が多く腸内で腐敗しやすい。古い油で揚げたものは避けたほうが無難。エビ天でアレルギーを起こす人は多い。
- <シュークリーム> 早く腐りやすいので、新鮮なもの以外、口にしないこと。
- <青梅> 猛毒の青酸が含まれています。特に、子供には食べさせないように。
- <サバ・カツオ・マグロ> 新鮮なものを少量にしておくこと。特に夏ものはあまりよくありません。
- <貝類> 時折、肝臓の弱いお年寄りが食べてアッという間に死亡してしまうケースがあります。ある種の菌が原因なのですが、肝臓の弱い人は貝類は火を通して食べる方がよいでしょう。特に、春先には注意。
- <カニ・タコ> 早く腐敗しやすいので、新鮮なものをなるべく早く食べること。
- <キノコ類> マツタケやシイタケでさえもまれに中毒を起こすことがある。名も知れないものは控えた方が無難。特に、胃腸の弱っている時は避けること。
- <水・アイスクリーム> おなかを急に冷やすので小さい子供は控えめに。アイスクリームは腸で腐敗しやすい。
- <うなぎ> 脂肪分が多く胃腸障害を起こしやすい。また腸内で腐敗しやすい。
- <罐詰> 賞味期限を守り、開けたらすぐに食べてしまうこと。取っておこうなどとは考えないこと。
- <納豆> 見た目にきれない色をしているものや少し酸味のあるものには要注意。
- <豆・もやし> 発芽中のものに毒素があります。
- <ジャガイモ> 「朝の金、昼の銀、夕の銅」と言われ、早いうちに食べるのがよいが、食べすぎると体を冷やすので、一日に多くて計五、六個が無難。